失敗して落ち込むことは誰でもあります。
大きなものであれば相当に辛い。
しかしそれを活かせるかどうかは成長できるかどうかに関わってきます。
本記事は、失敗の意味を説明するとともに、失敗にどう向き合うのが最善の策なのかを説きます。
「失敗は成功のもと」と言えるようになるための心構えです。
失敗に対する心構えは、仕事、転職活動、勉強、スポーツや対人関係など様々な場面で応用できる重要スキルです。
失敗によって学習・理解して成長する
失敗や間違いは誰だって嫌なものです。
ミスはミス。それ自体に意味はなく、できることなら人生から排除してしまいたい。
そう思うのは当然です。
しかし、失敗は実は学びに極めて重要な役割を果たします。
失敗には意味があり、自分にとってどういう意味があるかを示してくれる
大事なのは、間違いが意味を創り出してくれることだ。間違いが理解を形成してくれる。
アーリック・ボーザー『Learn Better 頭の使い方が変わり、学びが深まる6つのステップ』(英知出版、2018年7月)166ページ
失敗や間違いに直面するということは、自分の中で重大な意味があると頭の中で告げられることを意味します。
「ガーン!」とか「しまった・・!」と思うのは、自分の理解に変化をもたらす鐘の音なのです。
私たちは失敗すると、意味を探し求める。だから学びの効果がいっそう高くなる。
同上・167ページ
間違ってショックを受けない人はいません。
その間違いから学ぼうとするのです。
失敗・間違いは新しい思考習得に欠かせません。
間違いは思考の本質である。間違いは概念形成の核心だ。学び、専門知識を育てる際に間違いをおかすのは、それが理解するために必要だからだ。
同上・169
自分が新しい思考・行動様式を取り入れるには、たくさん間違いをすることになります。
ゴルフのスイングを変えたいなら、何度も練習してミスを経験し、それから修正をして学んでいくのです。
失敗によって新たな学びを得て成長する。
失敗は怖い・恥ずかしい・笑えない
誰もが失敗を嫌がるのは、不快だからです。
ミスが好きな人などいない。間違うと強烈に痛い思いをし、恥ずかしく、自信をなくす。言い間違いをしたり、頼まれごとをしそびれたなど、ごくささいな失敗でさえ、何年も頭を離れなかったりする。そういう意味で、ミスは自分がどんな人間かをつきつける。私たちの存在をおびやかすものだ。
アーリック・ボーザー『Learn Better 頭の使い方が変わり、学びが深まる6つのステップ』(英知出版、2018年7月)167ページ
自分1人で失敗して「ああ、自分はなんてダメなんだ」と思う。
それだけで済めばいいですが、それだけで済まないと多くの人は考えています。
他人がいるからです。
上司から失敗するなよと言われる。
スポーツで監督からミスすると怒られる。
テストの点数が悪いと親が不機嫌になる。
対人関係で失敗して嫌な思いをすることは数えきれません。
まさに失敗は自分の「存在をおびやかすもの」です。
それほど苦しいものなら失敗は避けたい。
「失敗は成功のもと?知るかよそんなの。失敗したくないんだよ俺は」となるのも無理はありません。
失敗があってこそ。失敗を受け入れる。失敗を次につなげる。

失敗するのはダメなことだ。こう皆思う。
でも多くの人は確実にミスをする。
それゆえ、失敗しないのがすごいとされます。
しかし、前記で述べた「失敗が成長に役立つ」、あるいは失敗こそが成長に不可欠だと考えると失敗がないというのはもったいない。
「私、失敗しないので」というのは、言い換えると「私、成長しないので」と言ってるのと変わりません。
実際には「失敗しない」というのは、全プロセスでミスがないということではなく、ところどころ些細なミスはあるけれども結果としては大失敗にはならないという意味であって、常に何もかもノーミスということではないのだと思いますが、それでもミスをしないのはもったいない。
失敗は成長の糧であり、うまく活用すべきです。
上達したいが、その上達したいことのどこに失敗や間違いがあるのかわからないという状況はよいものではありません。
英語でも語学でも仕事でも、今より成長したいが、どこをどう直していいかわからなければ、上達はかなり遅くなってしまいます。
英語なら「あ、さっき話した時に動詞を過去形にしてなかった・・!」という間違いに気づいてそれを修正することで高いステージにいけます。
失敗を前向きに受け入れて成長しようとした人物のエピソードとして、バスケットボールのスーパースターであるマイケル・ジョーダンのものがあります。

ジョーダンがNBAを引退した後、スキーをあるインストラクターに習ったときのこと。
ジョーダンはミスをするとそこが改善の機会とみて喜んだというのです。
彼はミスがクロスワード・パズルのようなもので、解けると宝石をもらったような気分になることを理解していた。
レイ・ダリオ『プリンシプルズ―人生と仕事の原則―』(日本経済新聞出版社、2019年3月)381ページ
さすがバスケの神様ジョーダンだ。
ミスをしたポイントこそが自分のレベルアップにつながる最重要ポイントであり、ミスという現実のイベントではっきりとわかったことを喜んだわけです。
失敗として現実に現れなければ仮説にすぎないですからですね。
そんなマイケル・ジョーダンには”Failure”という有名なナイキのCMがあります。
私はこれまで9000本以上のシュートを外してきた。300試合近く負けた。26回、勝負を決めるシュートを任され、失敗した。何度も何度も失敗した。だからこそ、私は成功する。
ーマイケル・ジョーダン
これこそが成功者の持つ「失敗と成功のメンタリティ」です。
失敗した、「だからこそ」(“And that is why”)。失敗と成功の因果関係がきちんと現れています。
すげーぜジョーダン。
失敗を気にしないという失敗
失敗を恐れるあまり、凡人はどうしてしまうのか。
失敗への対処としてこれをやってはいけないというのを紹介します。
①「まあいいや」と気にしない
これはよくありそうです。
また、アドバイスでも日常飛び交っていそうです。
精神的にずっと引きずらないようにするために気にしないのはメンタル上の対応として気にしないのは重要な対応です。
しかし、失敗が生じて脳内で「これ大事だぞ!」と警告がならされているのに、「よし!気にしない!」と無視するのはあまりよくありません。
自分の心のケアのために切り換えるやさしさは必要ですが、技術的にその失敗をどう活かすべきかの反省の機会がなければまた同じ間違いをしてしまいます。
いつも同じミスショットをするゴルファーが「いけね!まあいいや。次だ次」とすぐにミスを忘れていて、上達が見込めないのと同じです。
②失敗と認めない
これは自分を誤魔化す行為です。
テストで80点を目指すと宣言した。テストを受けて70点しか取れなかった。
そんなときに「今回は難しくて平均点も低かったから仕方ない」といって自己正当化する。
私の同業である弁護士にはこの手の自己正当化をする人が非常に多く見られます。
自分の非を認めない。
これは、成長の機会を自ら潰すことを意味します。
③失敗に気づかない
そもそも自分が間違ったことに気づかないということもよくあります。
独裁社長がおかしいことをやっていてもそのままになってしまうというのが例です。
自分のメール等の文章がおかしくても、何が悪いか全く気づいていないということも大いにあるでしょう。
自分の成長を願うのであれば上記は失敗という苦しい事象の捉え方としてもったいないです。
せっかく失敗したのであればうまく使いたい。
マイケル・ジョーダンのようにミスを喜んで成長の種が見つかったと喜ぶべきです。
失敗との向き合い方
しかし、ジョーダンのような神メンタルを持つ人は地球上でほとんどいません。
本記事では一般人向けの失敗への向き合い方を紹介します。
いずれも心理学者が提唱する向き合い方です。
3人の心理学者による3つの対処法を紹介します。
(1) 自分に語りかける「この失敗から何が学べるか?」
1つ目は、心の中で自分と対話することです。
「ああ、なんでそんな失敗をしてしまったんだ」という後ろ向きなことを問いかけるのではなく、前向きに将来の成長に向けた対話をしましょう。
失敗したら「これはチャンスだ、新しいことを学べる絶好の機会だ」と考えるのです。
そう考えて「この失敗から学べることは何か?どうしたらこの失敗から成長できるのか」と問いかけましょう。
ミスにわずらわされず、成長に目を向けよう、失敗や間違いはスキルや知識を獲得するチャンスととらえよう、と自分に語りかけるのだ。例えばミスをした後、自分に「ここから何が学べる?どうすれば成長できる?」と問いかけるとよい
アーリック・ボーザー『Learn Better 頭の使い方が変わり、学びが深まる6つのステップ』(英知出版、2018年7月)176ページ
本ブログのメインテーマである転職活動でいえば、面接が通らなかった場合には「どうしたら次はうまくいくか」と考え、修正するという対応が考えられます。
仕事でうまくいかなければ、「この失敗から何を学べるか」を考えるべきです。
(2) 失敗を予め見込んでおく
これは事前の備えです。
成長に困難はつきものです。
失敗だって当然ある。成長には失敗がつきものだとどこかのブログ記事に書いてあったじゃないかと思っておくことです。
そのため、ミスをしたとしても「想定通りだ」と思えばいいのです。
ウォーレン・バフェットの右腕であるチャーリー・マンガーは、幸せになる秘訣として「それは簡単だ。高い期待を持たないことだ」と述べています。
(3) 失敗する環境に飛び込め
3つ目のアドバイスはスパルタ式です。
成長したければミスをすべきであるが、人はミスを嫌がるのだから放っておいたらミスしない環境に行きたがる。
そのため、自らミスをする環境に身をおけというものです。
シアン・バイロックはさらに踏み込んで、もっと自分を追い込むべき、ミスをするかもしれない状況に身を置くようにすべきと主張する。「手をこまねいていてはだめです」と彼女は言う。人前で話すのが怖ければ、もっと人前で話せということだ。自分は数字が苦手だと思っているなら、もっと数字に関わってみる。レストランでチップの計算をする程度でもよい。
アーリック・ボーザー『Learn Better 頭の使い方が変わり、学びが深まる6つのステップ』(英知出版、2018年7月)176ページ
「できないから、やらない」ではなく、失敗が当然ありうる状況に身を置きなさいということです。
英語を話せるようになりたいなら、外国人と英語でやりとりする環境を作り出すといったことが考えられます。
転職に興味があり、現勤務先の文句を言う日々ならば、転職活動をやってみるべきです。
転職活動に失敗したって問題ない。
失敗は他人からも学べる
本記事の失敗は自分事を想定しています。
失敗からの学びは、他人の失敗からも得られます。
自分の人生でできる失敗の種類や数はあまり多くありません。
しかし他人の失敗から学べばたくさんの人の人生分の失敗を糧にできます。
ぜひ他人の失敗から学びましょう。

バフェットは、「読書は何物にも勝る」と言い、読書は著者とランチで話すようなものと表現しています。
マンガーは、他者の伝記を読むことを大いに勧めています。
偉大な人物の失敗を読み、「なんでそんな失敗をしてしまったのか。今後の自分なら同じような局面でどうすべきなのか」というのを問いかけて読めば伝記の読み方が深まります。







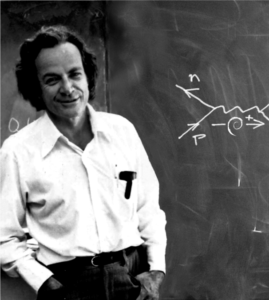


コメント