新人弁護士の法律事務所での文章作成OJTの一例です。
1 とある法律事務所での書面作成の流れ
準備書面等の裁判所に提出する書面を作成する場合、以下のような流れで書面を作成していました。
(1) ボスから方針の指示がある
自分で書面を勝手に書き始めることはありません。
クライアントが訴訟をする、クライアントが訴えられる、すでに係属している訴訟事件で次回までに当方が書面提出の予定になっている、といった書面作成の端緒があります。
書面作成をしなければならないとなると、ボスから「こんな書面を書け」と指示があります。
その方針指示に沿うべく下っ端弁護士が書面案を作成していきます。
(2) アウトラインを作成する
ボスから伝えられるのは方針だけであり、テンプレートが渡されるわけではありません。
基本的には白紙から考えます。
他の案件から書面データを流用することもありますが(時間短縮のためできたらそうしたいですが)、本件では残念ながら流用できる書面がなく、ゼロから書面作成をする場合を考えます。
いきなり書き始めるのはよくないため、まずどういう構成にしようか考えます。
- 何を書くべきか。これは書きたいが書かない方がいい書面に仕上がるか。
- これを先に書くべきか。この順番の方がいいか。
などなど色々考えながら、アウトラインを箇条書きします。
箇条書きだけの状態でボスにチェックしてもらう。
書面全部を書いてからチェックしてもらうのは避けた方がいい。
方向性が違うと全部ダメになって大いなる時間の無駄になる可能性が高いから。
この「アウトラインだけの状態の書面チェック」を嫌がるレビュワーが多いですが、レビューは早いうちにはじめ、レビュワーも一緒に文書作成者としての意識を持った方がいい。
出来上がった文書を読んで、「ふむふむ。。なんだこれは!なっとらん!やり直し!!」(ビリビリ)というパワハラは非効率すぎるし文書作成者として無責任すぎます。
文書で最初の構成が重要なのは言うまでもなく、構成を練り上げる段階に関与しないのは文書作成者としてお粗末というほかありません。
ボスの方針で、書面の見出しは「~について」というメッセージ性の乏しいものではなく、たとえば以下のような主張を含んだ書き方をしていました。
「第1 岸田内閣の「新しい資本主義」は「古い資本主義」の理解を欠いた砂上の楼閣である」
なので、見出しだけで骨格となる文書全体のメッセージを構成できるため、見出し案の表現もあれこれ考えてアウトライン案を作り上げます。
アウトライン案を作り上げたらプリントアウトしてボスに提出します。
(3) ボスのアウトライン添削
アウトラインの添削なので、ボスの添削はそんなに多くありません。
ボスが鉛筆で私のアウトライン案を修正します。
2~3回に及ぶこともありますが、書面本体に比べたら大した添削回数ではありません。
(4) 書面本体を作成する
アウトライン(見出し)が固まったら、いよいよ本文を書きます。
ワードでカタカタ打っていくのです。
関係書類や参考文献を見ながらワードファイル上であれこれ書きます。
当然時間がかかります。
- 引用する証拠書類をきちんと見れているか。
- 使う判例の事案はどうか。
- 相手の主張はどういうことか。
- この理論構成は破綻していないか。
- 裁判官にわかりやすいか。
様々なことを考えながら書き進めていきます。
悩みながら書くので、そんな簡単に進みません。
1文が長すぎるとか、主語と述語が離れすぎているとかそんなのも気になります。
文章ではなく表にして表現した方がいいかといったことも考えます。
どう説得するか考えるのは楽しみでもあるのですが、文章作成はなかなか辛いものです。裁判文書の作成が愉快だという人はあまりいないでしょう。
時間もかかります。かなりかかる。
他にやるべき仕事があるのに重たい文書作成業務がある時期は気が重くなります。
多くの弁護士がそうだと思いますが、日中はまとまった時間取れないため、夜に書面作成をすることが多かったです。
夜9時頃に事務所近くで1人で夕食をさっと食べて、「”今日”はまだ3時間ある」と考えて書面作成のために事務所に戻っていました。
同じ3時間なら昼間にやれよ、と思うのですが、勤務時間の長い職場では昼間の時間はぼーっとしがちです。
(5) ファーストドラフト作成後に何度も見直して書き直す
しんどいと思いながらもなんとか文書を書き上げる。
書き上げたからと言ってすぐにボスに書面を出したりしません。
草案を書き終えたら、何度も見直しをします。
どうやって見直すか。
プリントアウトし、紙媒体で自分の書面を読むのです。
画面で読むのと紙で読むのは違う。
ある弁護士は「書面をプリントアウトして紙でチェックしない奴は終わってる」とまで言ってました。
ファーストドラフトを当然最初は画面で見て、その後紙でも見る。自分1人でダブルチェック。
「なんか表現おかしいな」から誤字脱字もチェックする。
紙でチェックするとだいたい直す箇所が見つかる。
紙でチェックしたらワードファイル上で変更する。
第2版をまたプリントアウトする。
プリントアウトした文書を再度チェックする。
また直した方がいい箇所が見つかる。
再度ワードファイル上で変更して第3版を作る。
どこか直すと別のところも変更が必要になったりする。
当然紙に打ち出してまた第3版をチェックする。
もう直す箇所がなくなるか、あと1文字だけ直せばいいという段階まできたらワードファイル上で最終版を作ります。
何度も見直しては書き直す。プリントアウトする回数は通常5回ではすみません。
10回くらい見直すこともあります。
そして、最終版をA4サイズ、片面、2ページを1枚に集約、左上ホッチキス止めでプリントアウトし、ボスの机の上に出してファーストドラフト完了です。
このボスへのファーストドラフト提出前の自分一人で延々チェック時間が長い。
誤字脱字が多いとキレられるので、アソシエイトはみんな何度も提出前にプリントアウトしてチェックする。その結果、プリンターは大活躍。近くのごみ箱には膨大な紙ゴミが発生していました。
誤字脱字以外も内容がおかしいと指摘されるので、真剣に自分の文書を繰り返しチェックしてボスに提出するのです。
(6) ボスの本文添削
出来がよければボスの添削箇所は少ないです。
しかし、そんなうまくいくことはあまりありません。
最悪の場合は添削すらされず呼び出しを受けて、全部書き直しになることもあります。
そうでなければ鉛筆でかなり多くの修正指示を受けます。
(7) 添削を受けて本文を書き直す
ボスから無事(?)にたくさんの修正指示を受けたら、ボスの修正指示を見ながらワードファイルを書き直します。
ここは単にボスの指示どおりに直す。
「なんて書いてあるんだここ・・?」というものにも頭を悩ませながら、単純な指示ばかりであることを祈りつつ書き直していきます。
(8) 何度も推敲する
ボスの添削結果どおり書き直したからといって、文章全体が完璧なわけではありません。
ボスの大幅添削により文書全体が大きく変わっているので、添削指示がなかった場所も見て修正を加えなければなりません。
再度文書を見直します。
ファーストドラフトの時の見直しと同じように、プリントアウトして読んでみる。ボールペンで修正箇所を発見する。パソコンでワードファイル上で直す。
再度プリントアウトして紙で読む。ボールペンで修正する。パソコンでワードファイルを直す。
中々修正箇所はゼロになりません。
なんどもプリントアウトしては直しを繰り返します。
けっこうしんどい。
(9) ボスによる再コメントと書き直し、再々コメントと書き直し、再々々コメントと書き直し…(3,4回では終わらない)
第2版が完成したら、再度プリントアウトしてボスに提出します。
ボスが添削します。
ボスの添削結果を見て再度書き直します。
書き直したら、また何回も見直してプリントアウトしてボスに第3版を提出する。
ボスがまた添削する。
これが延々と繰り返されます。
簡単で短い書面なら繰り返しは少ないですが、難しい書面や長い書面だとやりとりが10回以上に及ぶこともあります。
(10) 完了までに本当に時間がかかる
淡々と書いてみましたが、実際にこの文章作成プロセスを体験すると本当に辛いです。
何より時間がかかります。
また、あれこれ考えて文章を作るのは非常に労力のかかる作業です。
その上、ボスの心理的プレッシャーもある。
相当にストレスフルなプロセスです。
2 スパルタ式文章鍛錬のメリット・デメリット
こんな苦しい文章作成実務のメリットとデメリットを考えます。
(1) 徹底添削を受けるメリット
他人から文章を見てもらえるだけでなく、ボスの文章をベースに文章の型を身につけることができます。
大いに学べました。
①ワードファイルで文章を作成する。
②プリントアウトしてボスに提出する。
③ボスが鉛筆で添削する。
④添削結果を見ながらワードファイルで修正する。
上記①~④のプロセスを見ると、②~④は無駄に思えます。
①ワードファイルで文章を作成する。
②ボス・2ってボスがワードファイル上で修正する。
上記①・②でやれば無駄がない。
しかし、紙でボスが添削して、それを見ながらワードファイル上で変更する作業は大いに意味がありました。
他人がワードファイル上で直すと、ファーストドラフトをした人は「あとはチェック係が完成してくれるだろう」と考えてしまい、文章の変更点にあまり関心を持たなくなってしまいます。
紙で帰ってきた添削結果を見ながら、自分で改訂版を作る作業で、どこが直されたのかに直視するようになるのです。
時間はかかるかもしれないですが、文章力アップには上記①~④のプロセスの方がいい。
アマゾン創業者のジェフ・ベゾスも文章作成には何度も見直して時間をかけることが大事だと言っています。

(2) 徹底添削のデメリット
徹底添削には当然デメリットもあります。
①しんどい
時間がかかります。
当然労力も相当なものです。
また、何回も直されるのは愉快なことではなく、精神的にも疲弊します。
文章を他人に直されるのは誰だって嫌です。
私は前述したような法律事務所で死ぬほど修正されまくっていましたので、修正内容が不合理でなければしょうがないと思います。
しかし他人に文章を直されると不当と感じて不満を述べる人は多いです。
私が働いた大手日系企業の法務部では、若手法務部員が文章を直されてブツクサ言っているのを耳にしました。
添削されるのに慣れていないので、少し文章を訂正されるだけで文句を言うのです。
どんだけ自分の文章に自信があるのか。根拠のない自信は怖い。
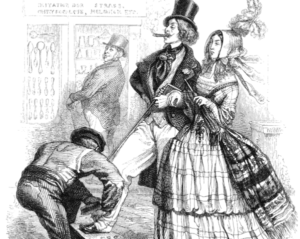
傲慢社員が文句を言うくらい、自分の文章を直されるのは自尊心を削られるものです。
②自分で考えなくなる
メリットで述べたように、添削者の文章の型を学べるのはとてもよいこです。
しかし、スパルタ式が激しいと、ファーストドラフトをする人は自分で考えなくなります。
ボスからの指示を受けてそれに従って文章を書く。
それを提出し、「違う」と言われて指示どおり書き直す。
これはボスの考える書面を作る代筆屋のような作業です。
そうするとこの書面を作成する目的のために書面を作成するのではなく、ボスにケチを付けられないようにするために文章を作ります。
ボスがきついとそうなります。
私のいた法律事務所の同僚は、ボスにキレられるのが嫌で遅くまで残って書面を作成していました。
同僚ともこのスタイルの文章作成では「全然自分の頭使わなくなる」と話していました。
超スパルタ・超管理式は、ある程度のところまでレベルを引き上げるのはよいかもしれませんが、自分で考えて文章を作るようになる、という観点ではいいことばかりではありません。
3 文章力
主に裁判官を説得する裁判書面をスパルタ式に徹底的に添削されて訓練された経験からすると、自分勝手な文章を書いている人が「文章力が重要」という言ってさも自分が高度な文章力があるかのように主張しているのを見ると違和感を感じます。
Twitterやブログで文章力がつくとか、気は確かかと思います。
好き勝手に文字をたくさん打ち込んでいたら文章がうまくなるとでもいうのか。
なるはずがありません。
バスケがすごく下手な人が、誰にも教わらず本やネットも見ずにやる気なく我流でジャンプシュートを1万本打ってもうまくなりません。
フリースローの成功率20%から40%にはなるかもしれませんが、40%という低い成功率が固定化され下手なのが常態化してしまうかもしれません。
文章がうまくなるには、過去の自分の作文法を常に否定しなければならず、愉快なものではありません。
ただ単に「あーたくさん書いた。疲れたなあ」と思うだけでは上達しないのです。
誰からも評価されず、直すこともない書きっぱなしの作文は、バスケ下手のシュート練習と変わりません。
よほど意識が高くない限り、その人の「下手な作文術」が常態化するだけです。
文章力を向上させるには、良い文章を読み、自分の文章を振り返って、良い文章にならって自分の文章を変えていかねばなりません。
そんな大変なことをする人はあまりいません。
なので多くの人の文章は読みにくい。
自分の思ったことを打ちこむだけであり、読み手のことを考えず、独りよがりなものになっているから。
文章力が高くなっても、楽に短時間で良い文章が書けるようになるとは思えません。
しかし、文章が上手な人は、時間をかけてじっくり考えて書くと文章下手より遥かによい文章を書くはずです。
良い文章をかけば、自分の考えがより他人に伝わります。
現代は視覚情報優位の社会であり、文字情報を上手に使えるスキルは未だに超重要です。
高い文章力は差がつくスキルです。













コメント